コーヒーの抽出科学との出会い:システムエンジニアだった私の転機
システムエンジニアとして働いていた5年間、私は常に論理的思考で問題を解決することに慣れていました。しかし、コーヒーに関しては完全に感覚頼り。「なんとなく美味しい」「今日は苦すぎた」といった曖昧な基準で淹れていたのです。
偶然手に取った一冊の本が全てを変えた
転機となったのは、退職を決意した29歳の春でした。書店でふと手に取った『コーヒーの科学』という本で、初めて抽出科学という言葉に出会ったのです。そこには、私がこれまで感覚で行っていたコーヒー抽出が、実は複雑な化学反応の連続であることが詳細に説明されていました。
お湯の温度が90℃と95℃では溶け出す成分が大きく異なること、豆の粒度(挽き目の粗さ)が0.5mm変わるだけで抽出時間が30秒も変化すること。これらの科学的事実を知った瞬間、エンジニア時代に培った分析力が一気に蘇りました。
データドリブンなコーヒー抽出への挑戦
その日から私は、コーヒー抽出を一つのシステムとして捉え直しました。抽出時間、水温、粉量、挽き目の4つのパラメータを変数として、毎日の抽出結果をエクセルで記録し始めたのです。1ヶ月で約50杯分のデータが蓄積され、自分好みの味を再現する「黄金比率」を発見することができました。
この体験が、後にコーヒーの専門学校で学ぶ理論的基礎と実践技術を結びつける重要な土台となったのです。
なぜ美味しいコーヒーが淹れられないのか?理論を学ぶ前の失敗体験
システムエンジニア時代の私は、コーヒーを淹れるのに何の理論も必要ないと思っていました。「お湯を注げば美味しいコーヒーができる」という単純な考えで、毎朝適当にドリップしていたのです。しかし、現実は厳しいものでした。
毎朝の失敗パターンが教えてくれたこと
当時の私のコーヒーは、日によって全く違う味になっていました。ある日は薄すぎて物足りなく、別の日は苦すぎて飲みきれない。特に印象に残っているのは、同じ豆を使っているのに3日連続で全く異なる味になった時のことです。
1日目:薄くて酸っぱい味
2日目:異常に苦い味
3日目:なんとなく美味しい(でも再現できない)
この経験が、私に「何かが根本的に間違っている」と気づかせてくれました。エンジニアとして論理的思考には慣れていたはずなのに、コーヒーに関しては完全に感覚任せだったのです。
見落としていた重要な要素
後に抽出科学を学んで分かったのですが、私は以下の基本的な要素を全て無視していました:
– お湯の温度:沸騰したお湯をそのまま使用
– 豆の挽き具合:購入時期によってバラバラ
– 抽出時間:気分次第で30秒〜5分まで変動
– 豆とお湯の比率:目分量で毎回異なる
特に致命的だったのは、お湯の温度管理を全くしていなかったことです。沸騰したお湯(約100℃)を直接注いでいたため、豆の雑味成分まで過剰に抽出してしまい、苦味ばかりが目立つコーヒーになっていたのです。
この失敗体験があったからこそ、後に科学的なアプローチでコーヒーを学ぶ重要性を痛感し、理論と実践の両輪でスキルアップしていく必要性を理解できました。
抽出科学の基礎知識:お湯と豆から複雑な味が生まれるメカニズム
コーヒーの専門学校で最初に驚いたのは、一杯のコーヒーが科学的に非常に複雑な現象だということでした。お湯と豆という単純な材料から、なぜこれほど多様で繊細な味が生まれるのか。その答えは抽出科学の基礎知識にありました。
溶解と抽出の二段階プロセス
コーヒーの抽出は、実は二つの異なる科学的プロセスが同時に起こっています。まず「溶解」では、豆に含まれる水溶性成分(酸味成分、糖分など)がお湯に溶け出します。次に「抽出」では、細胞壁から油分やタンニンなどの成分が引き出されます。
私が実際に学んだ抽出科学の核心は、時間軸による成分の出方の違いでした。最初の30秒で酸味成分が抽出され、1分後に甘味成分、2分以降に苦味成分が強く出てきます。この知識を得てから、抽出時間をコントロールすることで狙った味を作れるようになりました。
温度と粒度が与える科学的影響
お湯の温度は抽出速度に直接影響します。85度では穏やかな抽出、95度では活発な抽出が起こります。また、豆の粒度(挽き具合)は表面積を決定し、細かく挽くほど抽出効率が上がります。
実践では、浅煎り豆には高温で細挽き、深煎り豆には低温で粗挽きという科学的根拠に基づいた組み合わせを使い分けています。この理論を理解してから、失敗の確率が格段に減り、狙った味を再現できるようになりました。
温度・時間・粒度の黄金比:科学的データを実践で検証した結果
理論だけでは実際の味に結びつかないことを痛感した私は、抽出科学で学んだ温度・時間・粒度の関係性を徹底的に検証することにしました。システムエンジニア時代の実験精神が蘇り、同じ豆を使って3週間にわたって毎日データを取り続けたのです。
実験データから見えた最適解
毎朝30分早起きして、エチオピア産の豆で以下の条件を変えながら抽出を行いました:
| 抽出温度 | 挽き目 | 抽出時間 | 味の評価 |
|---|---|---|---|
| 85℃ | 中挽き | 3分 | 酸味が強すぎる |
| 92℃ | 中挽き | 4分 | バランス良好 |
| 96℃ | 中挽き | 4分 | 苦味が突出 |
最も印象的だったのは、92℃・4分・中挽きの組み合わせで抽出した時の味わいでした。理論通り、温度が高すぎると苦味成分が過剰に抽出され、低すぎると酸味が際立ってしまう現象を実際に体感できたのです。
忙しい社会人でも実践できる簡易測定法
毎日の実験で気づいたのは、温度計を使わなくても沸騰後の待ち時間で温度調整ができるということでした。沸騰直後から1分待てば約92℃、2分待てば約85℃になることを確認。朝の忙しい時間でも、この「待ち時間ルール」があれば科学的な抽出が可能になりました。
抽出科学の知識と実践データの組み合わせにより、理想的な一杯を再現性高く淹れられるようになったのです。この経験が、後の講師活動での実践的指導法の基礎となりました。
理論だけでは上達しない:知識と実践のバランスで見えた課題
理論を学んだ直後の私は、完全に頭でっかちになっていました。抽出科学の知識を詰め込んだものの、実際にドリップしてみると思うような味が出せない日々が続いたのです。
知識と技術のギャップに直面した3ヶ月間
特に印象的だったのは、グアテマラ産の豆で理想的な抽出を目指した時のことです。理論上は湯温92度、粉の粒度は中挽き、抽出時間4分で完璧なはずでした。しかし実際に淹れてみると、酸味が強すぎて飲みにくいコーヒーになってしまいました。
抽出科学の知識があるからこそ、「なぜうまくいかないのか」が分からず、かえって混乱していたのです。理論では説明できない微細な技術的要素—注湯のスピード、蒸らし時間の調整、粉の膨らみ具合の見極め—これらは実践でしか身につかないことを痛感しました。
バランスを見つけた転換点
転機となったのは、理論を一度忘れて「美味しいと感じる味」を素直に追求し始めたことです。同じ豆で毎日少しずつ条件を変えて、味の変化を舌で覚えることに集中しました。
| 実践期間 | 重視した要素 | 成果 |
|---|---|---|
| 1-2週目 | 注湯のリズム | 安定した抽出が可能に |
| 3-4週目 | 豆ごとの個性理解 | 理論を実践に応用できるように |
この経験から学んだのは、理論は「なぜそうなるのか」を理解するツールであり、実践は「どうやってそれを実現するか」を身につける場だということです。両方が揃って初めて、本当の意味でのコーヒー技術が身につくのだと実感しました。
ピックアップ記事


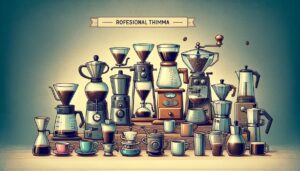
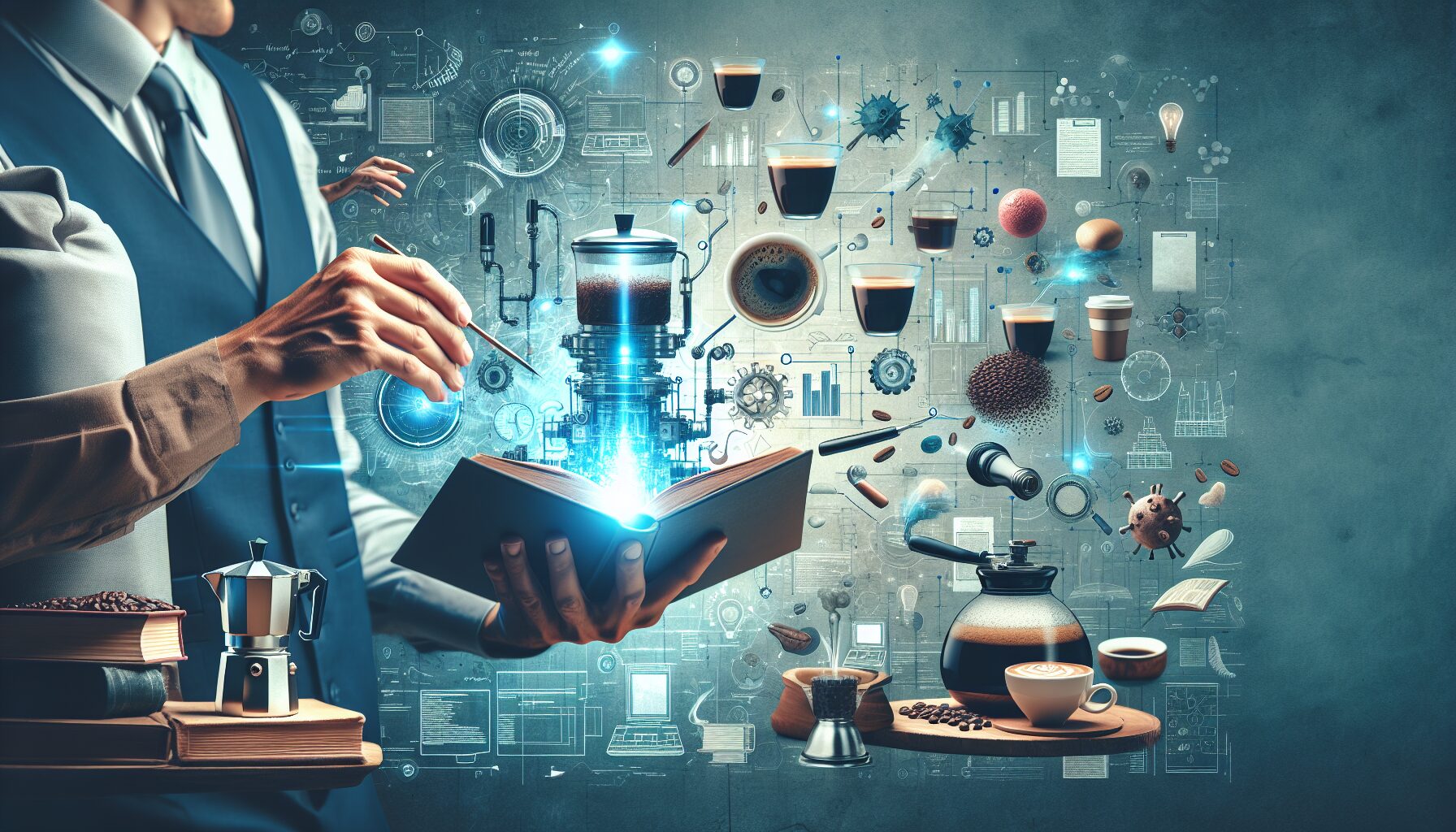
コメント